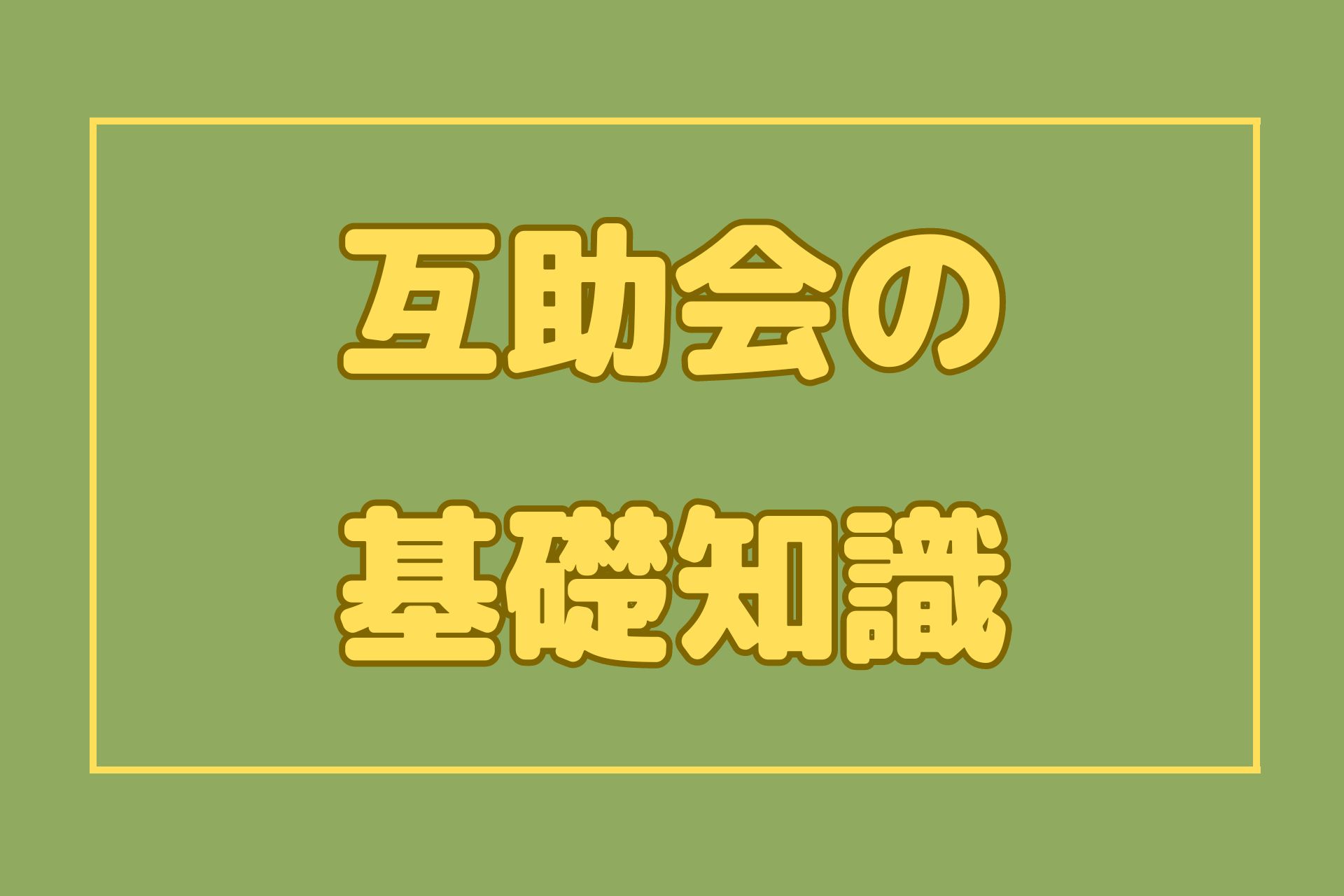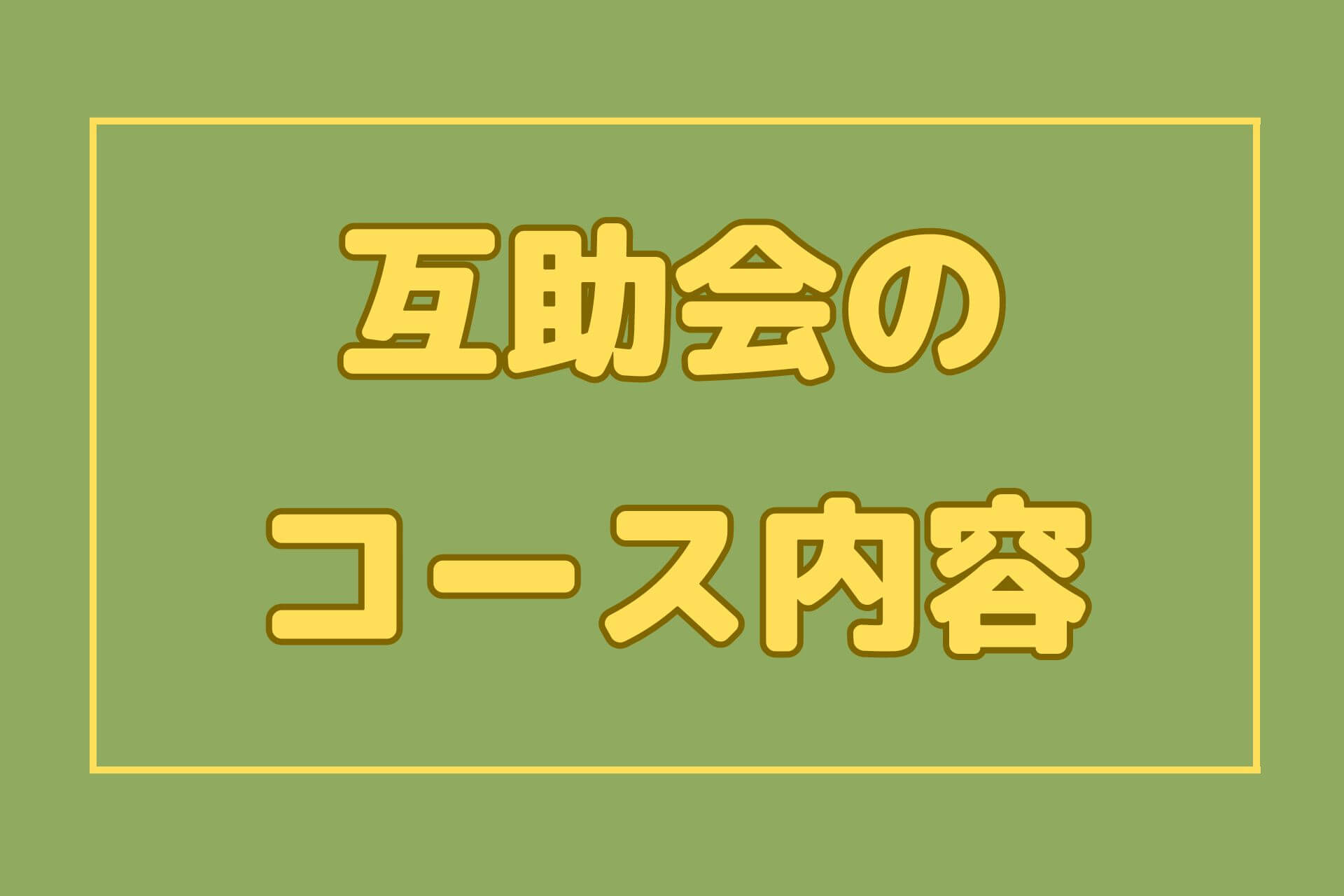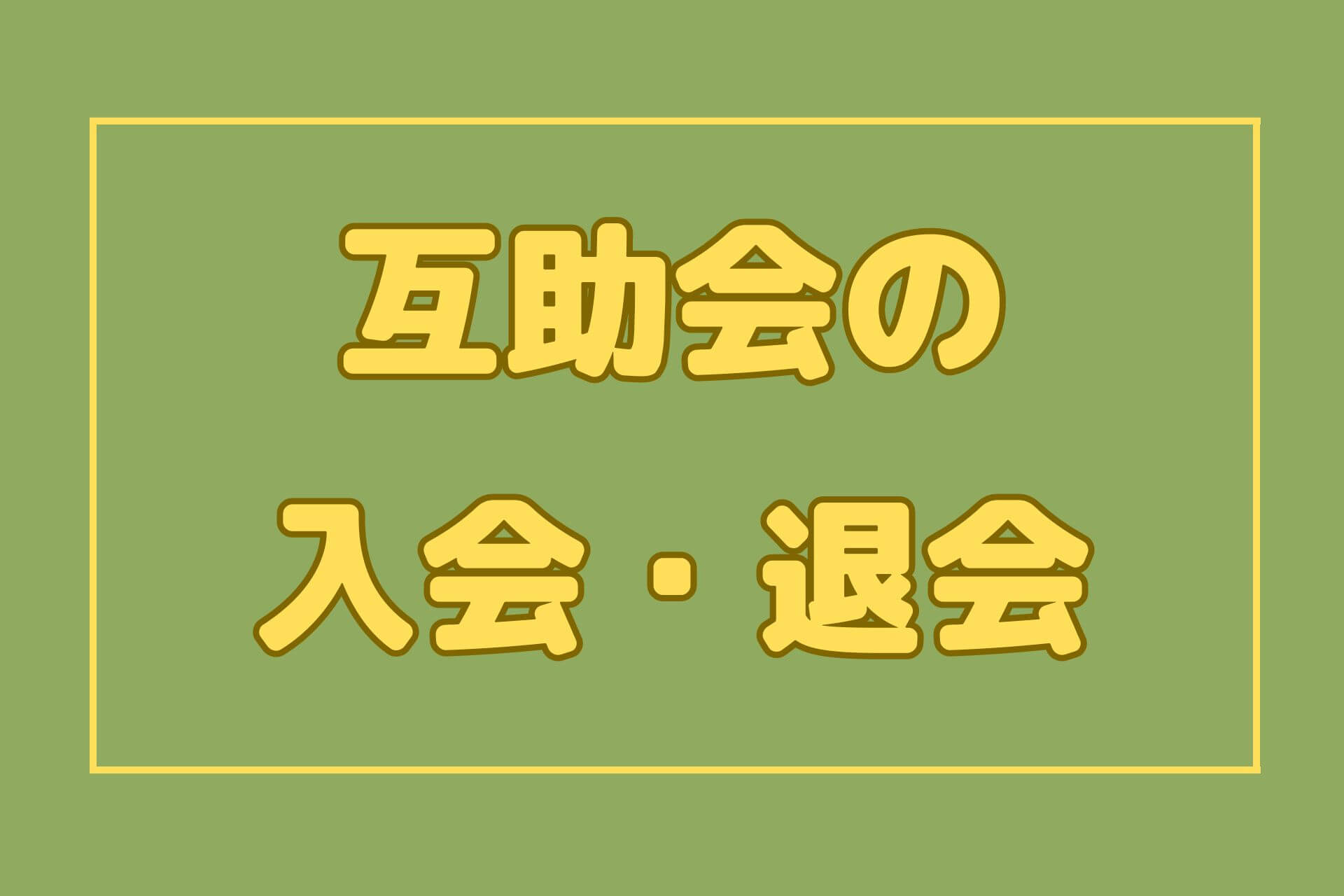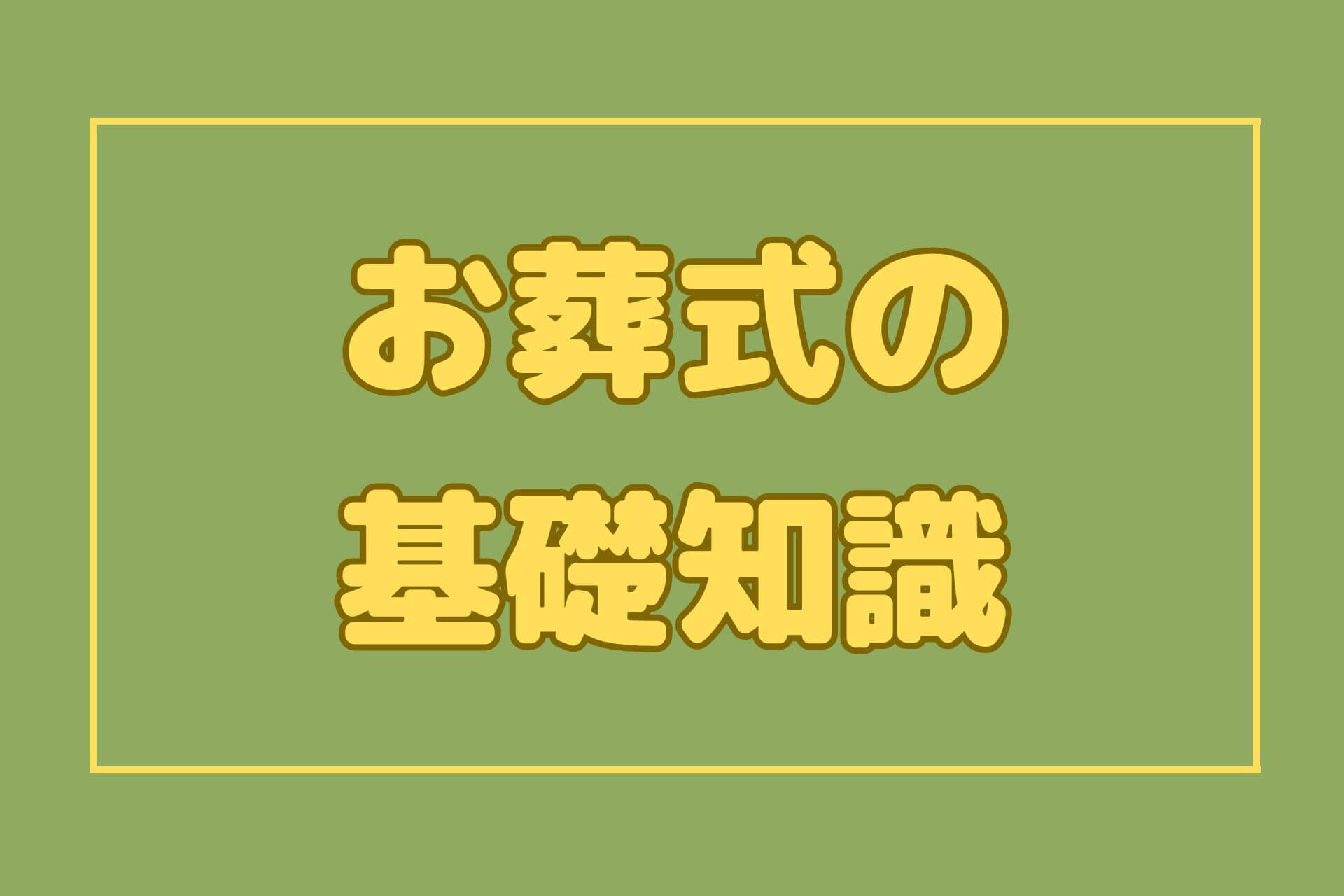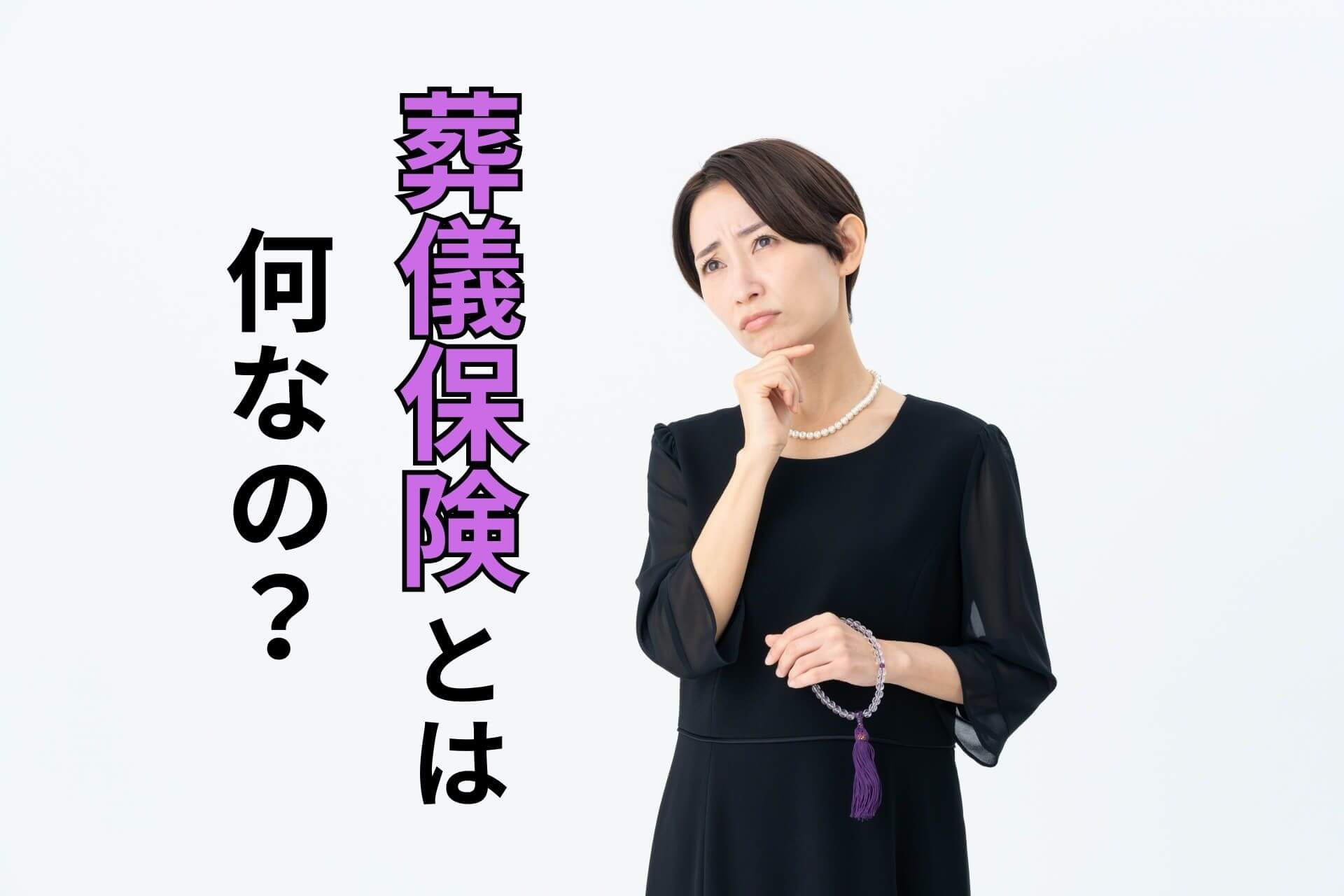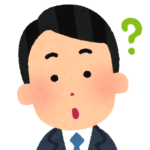
『葬儀保険』って何ですか?加入しておいた方がいいのでしょうか?
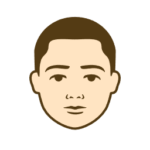
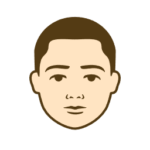
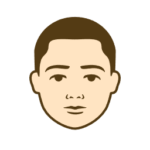
葬儀保険は互助会の積立てと併用すると便利ですよ。
最近ではインターネットなどで『葬儀保険』の宣伝が出ています。
あなたは今、生命保険や医療保険などいくつかの保険に加入していると思いますが、葬儀保険というのは馴染みがありませんよね。
葬儀保険に加入しておくと、お葬式をするときに保険金が支払われるので葬儀費用の負担を軽減できます。
お葬式にはたくさんのお金が必要なので、葬儀費用に関して不安がある方は最後まで読んでみてください。
- 葬儀保険の全体像が分かります
- 葬儀保険のメリットとデメリットが分かります
- 葬儀保険?そんなの初めて聞いた。
- 自分の葬式のときに家族の負担を少しでも減らしたい。
- 親戚なども招いてお葬式をしたいが、葬儀費用が心配。
この記事を書いている私『ちょっき』は僧侶になって30年です。お葬式を800回以上お勤めしてきた経験をもとに互助会に関する情報を発信しています。
葬儀保険とは
近年では『葬儀保険』という便利な保険があります。
葬儀保険とは、その名のとおり『葬儀費用に備える目的で、死亡時に保険金を受け取る保険』のことです。
要するに【葬儀費用をまかなう保険】だと思ってください。
葬儀保険は、
- 保険期間は1年以内
- 掛け捨て型
- 保険金額は300万円以下
- 80歳以上の高齢者でも加入できる
というのが一般的な内容です。
葬儀保険は保険期間が短いので、受け取れる保険金は少なくなりますが、それだけ少額での支払い(毎月600円程度から)が可能です。
受け取る保険金が少ないといっても、加入する保険によっては300万円まで受け取れるので、これなら葬儀費用へ充当するには十分な金額でしょう。
ちなみに、保険金は基本的に《受取人》へ支払われますが、保険会社によっては葬儀社へ直接支払ってもらうこともできます。
また、葬儀保険は80歳以上の高齢者でも加入できるのが嬉しいポイントです。
高齢者の場合は毎月の支払い金額が多くなりますが、葬儀費用の不安がかなり軽減されるでしょう。
葬儀保険は『絶対に必要』というものではありませんが、ある程度の年齢になれば【安心】のために加入してもよいと思います。
葬儀保険の種類
葬儀保険には、
- 保険金定額型
- 保険料一定型
の2種類あります。
保険金定額型
『保険金定額型』の葬儀保険というのは、その名のとおり【受け取る保険金額が一定の保険】のことです。
『保険金定額型』は契約を更新するたびに支払う保険料は上がりますが、受け取る保険金額は変わらない保険です。
葬儀保険は1年間の契約なので、毎年更新することになり、更新のたびに年齢も重ねることになります。
そして、『保険金定額型』は受け取る金額が変わらないため、契約を更新するたび、つまり年齢を重ねるたびに支払い金額が増えていきます。
また、受け取る金額は変わらないということで、高齢の人ほど初回の支払い金額は高くなります。
保険料一定型
保険料一定型は【月々に支払う保険料が一定の保険】です。
支払う保険料が変わらないので、家計への負担は変わらずにすみます。
また、支払う保険料が変わらないので、葬儀費用に対する計算がしやすいです。
しかし、支払う保険料が一定であるため、年齢を重ねるにつれ受け取れる保険金が減っていきます。
なので、葬儀費用の全額ではなく、葬儀費用の1部だけをカバーしようと考えている方には保険料一定型の方が適しています。
ただし、年齢を重ねるたびに受け取れる保険金も減っていきますので、どれくらい金額が減るのかを事前に知っておくことが大事です。
葬儀保険で支払う保険料の相場はどのくらい?
葬儀保険は、毎月少額ずつ支払うことが多いです。
月々に支払う保険料は、保険会社や加入した保険の内容によって異なりますが、相場としては、
1千円~1万円
くらいです。
毎月1千円の支払いであれば受け取る保険金は【30万円~50万円】くらいで、1万円の支払いであれば【300万円】くらいが相場となります。
ただし、あなたもご存じのとおり、保険というのは年齢によって月々に支払う保険料が大きく違うので、格安の金額を打ち出している宣伝には十分に注意してください。
葬儀保険のメリットとデメリット
葬儀保険にはいろんなメリットとデメリットがあります。
利用者にとってありがたいメリットが多い一方で、意外な落とし穴となるデメリットもあるので、よく比較検討してから加入することが大事です。
葬儀保険のメリット
まずは葬儀保険のメリットから紹介します。
葬儀保険のメリットは、
などがあります。
葬儀費用の補助ができる
葬儀保険に入っておけば、いざというときに『葬儀費用の補助ができる』のがメリットです。
葬儀費用は、お通夜とお葬式を行う『一般的なお葬式』であれば、お布施を含めて【210万円】くらい必要となります。
それだけ大きな費用を準備するのは大変ですよね。
しかも、人はいつ亡くなってしまうか誰にも分かりません、それが20年後かしれませんし、もしかすると明日かもしれません。
ですから、いざというときに『葬儀費用の補助』となる葬儀保険の入っておくと、あなた自身も家族も安心です。
支払う保険料が安い
葬儀保険は『支払う保険料が安い』ことが嬉しいメリットです。
葬儀保険というのは『少額短期保険』の1つです。
少額短期保険は、受け取れる保険料が【1,000万円以下】で、保険期間は【原則1年間】と決められており、そのため支払う保険料も少額になります。
保険料は保険会社やプランなどによって異なりますが、安いものだと月々の保険料が【600円】程度の保険もありますよ。
しかし、支払う保険料が安いというのは、若い年齢だったり、受け取る保険金が少ない場合であることがほとんどです。
葬儀保険を選ぶときには、どのような条件で、いくら支払って、いくら受け取れるのかをよく確認しておいてくださいね。
高齢でも加入できる
葬儀保険の大きなメリットとして『高齢でも加入できる』ということがあります。
葬儀保険は一般的な死亡保険とは違い、80歳以上でも加入できる保険がたくさんあります。
日本では高齢化が進んでおり、それにともない葬儀費用に不安を抱える高齢者も多いです。
しかし、高齢者でも加入できる葬儀保険があれば大きな安心材料になるでしょう。
保険金の支払いが早い
葬儀保険は『保険金の支払いが早い』というのがメリットです。
お葬式というのは死亡してから3日~5日後に執り行われることが多く、前金が必要な葬儀社もあるため、すぐに葬儀費用が必要となります。
葬儀保険というのは【葬儀費用をまかなう】ことを目的とした保険なので、保険会社は迅速に対応しなくてはいけません。
そのため、保険会社は、加入者が死亡したことを確認できるとすぐに保険金を支払ってくれます。
また、保険会社によっては《申請した翌営業日》に保険金を支払うところもあるので、保険加入のときには保険金が支払われるタイミングを確認しておきましょう。
医師の診断書がなくても加入できる
葬儀保険には『医師の診断書がなくても加入できる』というメリットがあります。
葬儀保険は少額短期保険ということもあり、医師の診断書を提出しなくても加入できるものが多いです。
そのため、加入のときには簡単な健康告知だけでよい、または健康告知そのものが必要ないということになります。
一般的な保険は、加入時に医師による診断書を提出する必要があり、場合によっては保険に加入できないことがよくあります。
しかし、葬儀保険であれば医師の診断書が不要なので、仮に《持病がある》などの健康上の不安があっても加入できるので、加入者本人だけでなく家族も安心です。
保険期間が1年間なので、保障の要・不要が見直しやすい
葬儀保険は『保険期間が1年間なので、保障の要・不要を見直しやすい』というメリットがあります。
葬儀保険は、原則として保険期間が1年間と決まっているため、毎年更新をしていくことになります。
どんな保険もそうですが、定期的に『保険の内容を見直す』というのはとても大事です。
あなたの希望と保険内容が違っていれば、保険の解約をしたり、もっとよい内容の保険に乗り換えるなどの対策が必要です。
葬儀保険は毎年《更新するかどうか》を決めますので、そのときの家庭の状況に合わせて保険の要・不要を見直すことができます。
葬儀保険のデメリット
続いて葬儀保険のデメリットを紹介します。
葬儀保険のデメリットには、
などがあります。
『掛け捨て型』の保険である
葬儀保険は『掛け捨て型』の保険であることがデメリットとなります。
一般的な保険の『貯蓄型保険』だと、保険料を一定期間を支払っていれば解約時に《返戻金》があります。
一方で、葬儀保険は『掛け捨て型』なので支払った保険料は戻りません。
じつは、葬儀保険の保険料が安かったり、高齢者でも加入できるのは、葬儀保険が『掛け捨て型』だからなんですよね。
支払った保険料は戻りませんが、その分だけ【安心を買っている】と考えてみてください。
年齢によって支払う保険料や受け取る保険金が変わる
葬儀保険の大きなデメリットは『年齢によって支払う保険料や受け取る保険金が変わる』ということです。
保険と年齢は密接に関係しています。
決まった金額を受け取る場合、年齢が上がれば支払う金額も上がっていきます。
そして、決まった金額を支払う場合、年齢が上がれば受け取れる保険金は下がっていきます。
また、そのときの年齢によっては保険そのものに加入できません。
他の保険でも同じですが、何歳でいくら支払い、何歳でいくら受け取れるのかをしっかりと確認しておきましょう。
支払い期間が長いと損をする
葬儀保険は『支払い期間が長いと損をする』というデメリットがあります。
葬儀保険で受け取れる保険金は少額です。
そのため、長期間支払い続けると、支払った金額よりも受け取る金額の方が少なくなる可能性があります。
人はいつ亡くなるか誰にも分からないので、いざというときのために備えておきたいですよね。
しかし、あまり若い年齢から更新し続けると、逆に損をしてしまうこともあるので注意しましょう。
保険契約者保護機構制度の対象にならない
葬儀保険のデメリットには『保険契約者保護機構制度の対象にならない』という点が挙げられます。
日本には【保険契約者保護機構制度】という制度があります。
保険契約者保護機構制度とは、保険会社が倒産したときに、その保険会社が『生命保険契約者保護機構』や『損害保険契約者保護機構』から資金援助を受けて利用者の保険契約を引き継ぐ制度です。
簡単に言うと『保険契約者を保護する制度』です。
この制度により、加入してる保険会社が倒産してしまっても、利用者は他の保険会社から《倒産した保険会社と契約した内容と同等の保障》を受けることができます。
しかし、葬儀保険のような少額短期保険を扱う保険会社が倒産した場合、保険契約者保護機構制度の対象になりません。
とはいえ、少額短期保険には『供託金制度』が設けられています。
保険会社は、事業開始時に国へ1千万円の供託金を預け、その後は段階的に供託金を積み増しする必要があり、万が一のときには必要資金の補填などに充てられます。
生命保険料控除の対象にはならない
葬儀保険は『生命保険料控除』の対象にならないのがデメリットです。
少額短期保険は税法上『生命保険料控除』の対象外となっているため、年末調整や確定申告で保険料控除は受けられません。
ですから、毎月の支払金がそのまま家計の負担になってしまいます。
葬儀保険の支払い保険料が安いのは、このような税制上で不利な点もあるからなんですよね。
互助会の積立てと葬儀保険を併用する
葬儀費用の準備の手段は葬儀保険だけではありません。
【互助会】に入会し、事前に積立てをしておくことで葬儀費用の対策ができます。
互助会で積立てをしておけば、お葬式のときに大幅な割引などの《お得なサービス》が受けられるので、葬儀費用の負担を軽減できます。
なので、葬儀費用の対策として『互助会の積立てと葬儀保険を併用する』というのも有効な手段だと思いますよ。
ただし、互助会はあくまで《お得なサービス》を受けるためのものであり、現金が支払われるわけではありません。
一方で、葬儀保険は保険料という形で『現金』を受け取れます。
ですから、お得なサービスと現金を併用することで効率よく葬儀費用の対策をするわけです。
当サイトでは何度も言っていますが、互助会の積立てだけでは葬儀を執り行うことはできず、必ず何らかのメニューの追加が出てきます。
そして、メニューを追加するためには追加金が必要です。
ですから、互助会の積立てによってお得なサービスを受けつつ、不足分を葬儀保険でまかなうのが効率的だと思います。
まとめ
葬儀保険は【葬儀費用をまかなう保険】で、
- 保険金定額型
- 保険料一定型
の2種類あります。
『保険金定額型』は、年齢が上がるにつれて支払う保険料が高くなり、『保険料一定型』は年齢が上がるほど受け取る保険金は安くなります。
月々に支払う保険料は、安いと600円程度のものがありますが、相場としては【1千円~1万円】くらいです。
葬儀保険のメリットは、
などがあります。
反対に、デメリットには、
などがあります。
葬儀費用の対策として、葬儀保険の他にも【互助会を利用する】という方法があるので、互助会と葬儀保険を併用するとよいでしょう。
※こちらの記事も読んでみてください。